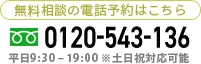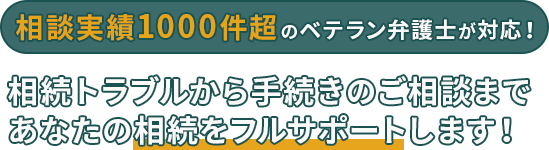| 亡くなられた方 |
父親 |
| 相続人 |
長男、二男 |
| 財産(遺産) |
自宅不動産の持分、預貯金、住宅ローン |
ご依頼の背景
依頼者の亡くなった父親の相続事件でした。相続人は長男、そして依頼者である二男でした。依頼者は自分で調停を申立てをし、既に5,6回の調停期日が行われていましたが、思うように調停が進まず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
亡父の主な遺産は長男と共有である自宅不動産(土地、建物)の持分、そして比較的少額の預貯金でした。
調停では長男から依頼者の取得分は約100万円程度であるとの主張がなされていました。
依頼人の主張
依頼者は遺産である自宅不動産の兄の持分、同居していた長男は亡父親から生活の援助等を受けていたとして、長男に多くの特別受益があったことと主張していました。また、長男が受け取った生命保険金は特別受益に準じて持戻しすべきことなど、多くの主張をしていました。
サポートの流れ
依頼者の調停での主張は多岐にわたっていました。そのため依頼者の主張が調停委員に十分に理解されない状態で調停が進んでいました。
そこで依頼者と相談しながら、証拠資料に照らして仮に審判になった場合に裁判所に認められる可能性のある主張をだけに整理することにし、争点を自宅不動産の持分に対する特別受益、生命保険金の持戻し等に絞り込みました。
結果
調停委員も代理人がついたこと、主張を整理し、証拠も提出したことから、こちらの主張を調停委員も十分に理解し、こちらのペースで調停を進めることができました。
実質的に長男の自宅不動産の持分が特別受益に当たること、生命保険金についても持戻しとして評価することを前提として話し合いが行われました。
長男は代償金を支払うだけの十分な資産はなく、仮に調停が不成立になり、審判になった場合、遺産である自宅不動産の持分は形式競売になる可能性がありました。競売になると競落価格は時価よりも大幅に下がり、結果的に依頼者の取得分の少なくなる可能性が高くなります。
したがって、この事案は調停で解決することが望ましい事案でした。依頼者も私のアドバイスを受け入れて下さり、最終的に依頼者は約1000万円の現金を取得する内容で遺産分割調停が成立しました。
その他の解決事例
| 亡くなられた方 |
父親 |
| 相続人 |
長男、長女、二女 |
| 財産(遺産) |
預金、借入金等 |
| 亡くなられた方 |
母親 |
| 相続人 |
長男、二男、長女の子(代襲相続人) |
| 財産(遺産) |
自宅不動産、預金、現金など |
| 亡くなられた方 |
夫 |
| 相続人 |
妻、兄弟姉妹及びその代襲相続人 |
| 財産(遺産) |
自宅不動産、預貯金 |